
|
現在の民法では、法定相続人を、第一に被相続人の配偶者、第二に被相続人の血族(子ども・親・兄弟姉妹の順)としています。配偶者は常に相続権をもっていますが、血族のうち誰が相続人になるかについては、優先順位が定められており、上の順位の相続人がいる限り、下の順位の相続人に相続権はありません。(図30)
なお、孫や兄弟姉妹の子が相続する場合がありますが、これは相続人の相続分を相続人に替わって相続するものであり、「代襲相続」といいます。
相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が財産を受け継ぐ割合を「相続分」といいます。
被相続人が遺言で相続分を指定していれば、基本的にはそれに従うのが原則ですが、遺言がない場合には、民法が定めている「法定相続分」に従って相続します。なお法定相続分は、だれが相続人であるかによって、その割合が異なってきます。(図31)
しかし民法では、遺言によっても相続人から奪うことのできない、最低限度相続できる財産を保障しており、これを「遺留分」と呼びます。
遺留分の権利をもつ人は法定相続人に限られていますが、法定相続人であっても被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
残された財産を具体的にどう分けるかは、原則として相続人全員の話し合いによって決定しますが、話し合いでは解決できない場合もあります。
現行の民法では、子どもには均等の権利を与えており、肢体不自由である子どもにも必要な財産が充分にわたるのであれば特に心配はありませんが、そうでない場合には遺言書などで財産の分割方法を決めておくことも必要かも知れません。
このように被相続人は、相続でどの財産を、どのくらい、誰に相続するかも日頃からよく考えておかなければなりません。
図30法定相続人の優先順位
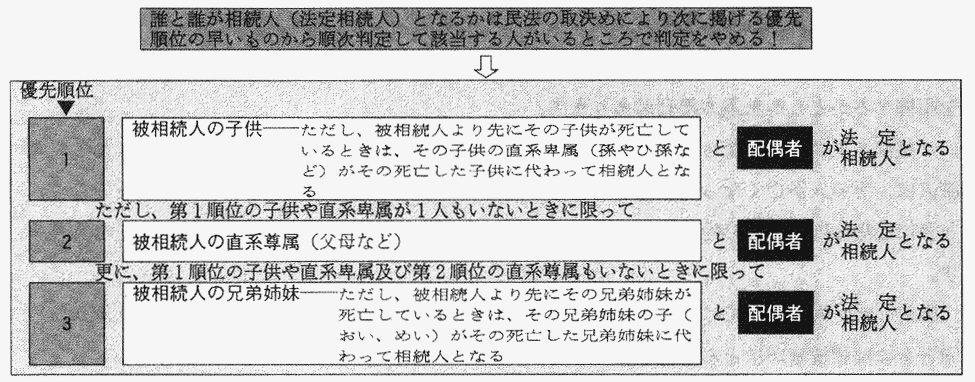
前ページ 目次へ 次ページ
|

|